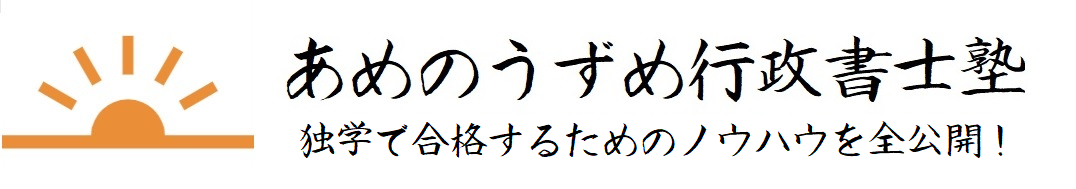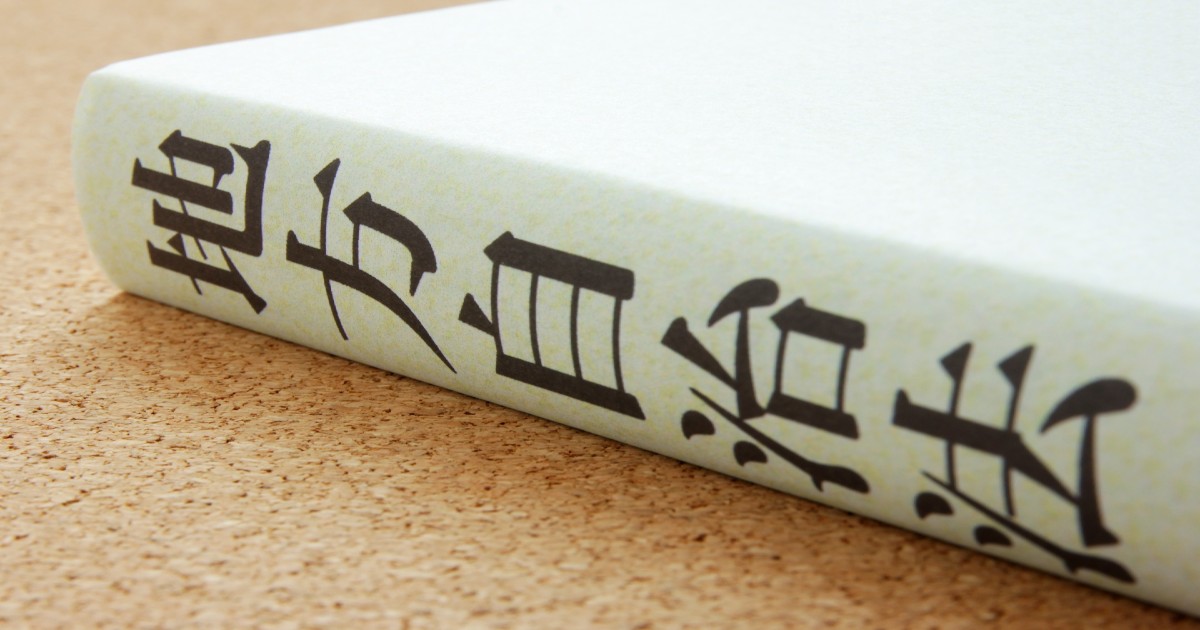行政書士試験の最重要科目といえば行政法ですが、
その行政法の中でも、特に苦手とする受験生が多いのが地方自治法です。
今回はこの悩ましい分野の攻略法について解説いたします。
この記事を読めば、地方自治法の概要と対策法がわかります。
地方自治法の概要
地方自治法は行政法に分類されてはいますが、ほぼ独立した1分野と考えた方が良いでしょう。
難易度的にはいたって普通で、易しい問題から難しい問題まで幅広く出題されます。
出題数は、例年、択一式で3問です。ただし、年によっては多肢選択式問題、記述問題として出題されることもありますので、残念ながら捨てるのはおすすめしません。
地方自治法は理解よりも正確な記憶が求められること、そして、条文数が多く、範囲が広いことも特徴です。
地方自治法が苦手な受験生が多い理由
『行政書士試験 地方自治法』で検索すると、関連するキーワードに『捨てる』の文字が含まれます。
これはつまり、地方自治法を捨てたいと考えている受験生が多いことを表しています。
なぜ地方自治法を苦手とする受験生が多いのでしょうか。
その理由は大きく分けて3つあります。
勉強量が多い
地方自治法が苦手な理由で1番多いのがこれです。
地方自治法は範囲がとにかく広いため、勉強するのが大変です。
これに追い打ちをかけるのが、その暗記量の多さです。
さらには量だけでなく、各手続きごとの議員の数や提出期間等細かい所の記憶まで求められるのも苦手になる要因です。
地方自治法が登場する順番
市販のテキストの多くは、行政法の一番最後に地方自治法を記載しています。
一般的な法理論(行政法総論、行政組織法等)、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法と一生懸命勉強してきた後で、さらにこのボリュームのある分野が登場するのですから、気持ちが折れるのも無理はありません。
その上、例年たった3問程度しか出題されないことが、勉強したくなくなる気持ちに輪をかけています。
関連する内容が少ない
地方自治法は他の行政法の分野とは少し毛色が違います。
例えば行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法といった法律は、行政側が行う内容やそのルール、制限、救済措置等に関係する内容であるのに対し、地方自治法は選挙の仕組みや議会運営等、どちらかと言えば憲法に近い内容が含まれます。
毛色の違う内容が急に現れ、苦手意識を持ってしまうケースです。
範囲としては行政法ですが、独立した分野と考えて勉強を進めましょう。
地方自治法の対策
地方自治法では正確な知識が求められますが、その全てを丸暗記しようとすると挫折してしまいます。
そこで、適当な理屈をつけて覚えやすくする方法が有効です。
具体例として、受験生が混乱しやすい直接請求の連署要件で試してみます。
地方公共団体(県や市町村等)への直接請求は6つあります。
※6つ・・・条例の制定・改廃請求、事務監査請求、議会の解散請求、議員の解散請求、長の解職請求、主要公務員の解職請求
その内、連署要件が有権者の3分の1以上のものと有権者の50分の1以上のものに分かれます。
ここで、人の地位を奪うものは乱発されると議会運営が成り立たなくなるため3分の1以上、それ以外は50分の1以上と理屈をつけるとどうでしょうか。
丸暗記と比べてかなり覚えやすくなる上に、混乱せずにすみます。
暗記が苦手な方は是非お試しください。
当サイトでは地方自治法の攻略情報を載せています。(執筆途中ですが…)
覚えやすいように理屈をつけて説明していますので、よろしければご利用ください。

行政書士試験 地方自治法まとめ
地方自治法は行政書士試験で行政法に分類されていますが、独立した一分野として考えましょう。
3題(択一式)しか出題されないことが多いですが、記述問題や多肢選択問題として出題の可能性もあるため、捨てるのはおすすめできません。
細部までの正確な記憶が求められますが、丸暗記で対応するのではなく、適当な理屈をつけて覚えるようにしましょう。
やればやっただけ得点に繋がる分野でもありますので、しっかりと勉強しましょう。
覚えるのに苦戦している方は、当サイトの『地方自治法 攻略』のページをご確認いただくか、当塾のにご相談ください。