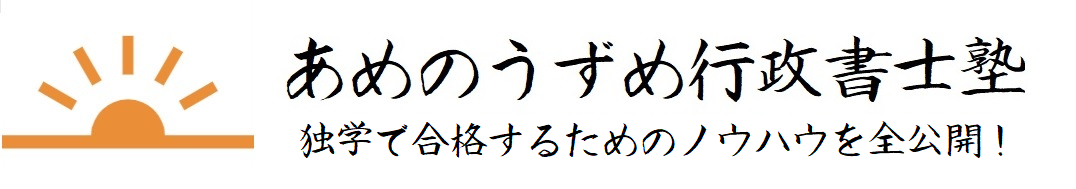行政書士試験に独学で挑むための情報を知りたい。
これから行政書士試験を独学で頑張りたいけど、いったいどこから手を付けたらいいのかわからない。
独学で頑張りたい気持ちはあるけど、手順がわからない。具体的な方法を知りたい。
この記事ではこういった疑問に答えます。
行政書士試験の独学攻略法
1:目標設定:行政書士試験に独学で合格
2:環境準備:参考書、問題集、勉強道具を揃える
3:基礎理解:行政書士試験の概要を知る
4:学習手順:参考書学習⇒問題演習
5:実践練習:過去問演習、模試演習
記事の信頼性について
記事を書いている私は、令和2年度の試験に学習期間5か月、独学で1発合格。
現在は行政書士として日々活動しています。
自分で試して実際に効果があった方法、モノだけを記載しています。
読者さんへの前置きメッセージ
本記事は「これから行政書士試験を独学で頑張りたいが、どこから手をつけていいか分からない」方に向けて書いています。
この記事を読むことで、「行政書士試験に独学で挑む際の具体的な始め方、その後の勉強法」までをイメージできるようになると思います。
「会社勤めの生活から脱却したい」と感じていた私を救ってくれたのが行政書士資格です。
行政書士資格で人生が変わった私が、感謝の気持ちを込めつつ、記事を執筆します。
それでは、さっそく見ていきましょう。
目標設定:行政書士試験に独学で合格

目標設定は、「行政書士試験に独学で合格する」ことです。
行政書士資格は新しく事業を始めたり、周囲の評価を高めたり、人生の選択肢を増やす道具です。
「行政書士資格」が欲しい人で、どうしても独学で合格したい人以外は独学で行政書士試験に合格することを目指しつつ、学習環境の変化や学習の進捗状況によっては、予備校や資格学校を活用するのもありですね。
なお、おすすめの資格学校は「厳選!!行政書士講座」にまとめており、無料体験とかも多いので、独学と比較検討しつつがいいかなと思います。
環境準備:参考書、問題集、勉強道具を揃える
行政書士試験を独学で頑張る人にとって、参考書、問題集、勉強道具ほど合格を左右するものはありません。
ここがしっかりとクリアできれば限りなく合格の可能性は高まります。
そこで、この3種の神器について詳しく説明いたします。
参考書、問題集
完全初心者の方のよくある疑問「参考書や問題集はどれを使えばよいかわからない」
この疑問についてお答えします。
まず参考書ですが、基本的には【自分に合った参考書】であればどれでも良いです。
自分に合うかどうかの判断基準は、
・文章の分かりやすさ/文章が頭に入って来やすいかどうか。
・構成/説明は絵が主体か文章が主体か。
・説明の長さ/説明はコンパクトにまとめられているか、理由まで深く説明されているか。
・書籍の厚さ/薄い参考書か厚い参考書か
で選びましょう。
そして、基本書を必ず1冊用意しましょう。ポケット六法が付属しているものが好ましいです。
※大手予備校が出版しているものには大体付属しています。
問題集については浅く広い総合問題集よりも、一つの分野を深掘りしている問題集をおすすめします。
その理由は行政書士の試験では細かい内容まで出題されることが多いため。
浅く広い理解では太刀打ちできない可能性があるので、一つの分野を深掘りしている問題集の方が適しています。
こちらも自分に合った問題集であれば、どの問題集を使っても大丈夫です。
それでも選びきれない人や失敗したくない人は、私がおススメする参考書、問題集を「厳選!!参考書&問題集」」の記事でまとめていますので参考にどうぞ。
勉強道具
勉強道具の中で特にこだわって欲しいのが、筆記用具と睡眠用具です。
この2つは勉強の継続、モチベーションの維持、学習効率の向上にとても大きな役割を果たします。
順に見ていきましょう。
■筆記用具
ペンは学習を精神的な面でサポートしてくれます。
書きやすいペン、持ちやすいペン、高級感のあるペン。
人それぞれ好みはあるかと思いますが、自分の手になじむペン、持ちたいと思えるペンを選ぶようにしましょう。
好きなペンを買うと、不思議とペン握りたいという気持ちになり、そのペンで勉強してみようという気持ちさせてくれます。そしてその効果は当分続きます。
これを応用し、勉強のやる気が出ない時に、新しいペンに変えるだけでやる気を出す方法もあります。
このように、長期的な勉強を行う際には、ペンの効用を使わない手はありません。
是非、ペンにはこだわるようにしてみてください。
ペンのスゴイ効用については「勉強時におすすめのペン」の記事をどうぞ。
>>>楽天市場でおすすめのペンを探す
■睡眠用具
睡眠の重要性を認識している受験生はまだまだ少ないのではないでしょうか。
睡眠は勉強と同じぐらい本当に大切なものです。
睡眠は感情の安定や集中力の維持といった勉強に欠かせない部分をサポートしています。
そしてまた学習した内容を整理し、記憶する役割も担っています。
このような重要な役割を果たしている睡眠を欠かすとどうなるか。
・学習効率が大幅に下がる
・眠くて勉強できない
・日常生活でも些細な事でイライラしてしまい、勉強する気分にならない。
受験生にとって、致命的なダメージを負うことになります。
そうはいっても、働きながらでは睡眠時間を確保するのが難しいこともあるかと思います。
私も働きながら勉強していたのでその気持ちはよくわかります。
だからこそ、質の高い睡眠を得る為に睡眠用具にこだわって欲しいのです。
私は勉強を始めて直ぐに枕とマットを購入し、質の高い睡眠を心掛けました。
これが本当に功を奏しました。
これから学習を始める方は睡眠時間を確保する。
それが難しければ質の高い睡眠を得られるように道具を調える。
これを必ず実践してください。
ゴッドハンド整体師の作った『整体枕』基礎理解:行政書士試験の概要を知る

行政書士試験に挑む前に必ず知っておいて欲しいことは
・行政書士試験は絶対評価の試験であること
・行政書士試験には明らかに重要である科目とそうでない科目があること
・記述式、多肢選択式、読解式が含まれていること
・足切り制度があること
の4つです。
行政書士試験は絶対評価の試験であること
行政書士試験は絶対評価の試験で、6割以上の得点ができれば合格できる試験です。
これはつまり、他の受験者のレベルに関係なく、自分に実力があれば合格できる試験であることを意味します。
他の雑音に惑わされず、粛々と自分のやるべきことをやりましょう。
※記述問題で調整されることはありますが、記述点抜きでも合格点以上を取れることから、基本的には自分の実力で合格できる試験と言えます。
行政書士試験には明らかに重要である科目とそうでない科目があること
行政書士試験では出題科目の点数配分に大きな偏りがあります。
これをしっかりと認識しておかなければ、勉強の優先順位を間違えてしまいます。
どの科目を優先的に勉強すべきか必ず把握するようにしましょう。
このあたりの話は、「行政書士試験 勉強の順番」」の記事で解説しています。
記述式、多肢選択式、読解式が含まれていること
行政書士試験では5肢択一問題だけでなく、記述式、多肢選択式、読解式の問題が出題され、そのどれもが合格を左右する程の重要な問題です。
記述問題については、文章をまとめる練習を重ねなければ得点できるようになりませんし、
読解問題については読解力や解答力をつけるのに継続的な学習が必要です。
自分が得意な問題形式、苦手な問題形式を予め知っておけば対策ができますので、出題形式については先に把握するようにしましょう。
足切り制度があること
行政書士試験には足切りの制度があります。
足切り制度とは、基準点以上の得点が出来なければ、総得点が合格基準点を超えていても不合格になってしまう制度です。
この制度がある為に、配点が低く、範囲も広い一般知識分野の勉強を疎かにできません。
幸いにも、一般知識は継続して学習すれば得点が易しい分野でもあります
行政法、民法と言った主要科目の学習を軸としつつ、一般知識分野も継続して学習するようにしましょう。
詳しい学習方法については、「行政書士試験 一般知識勉強法」」の記事で解説しています。
学習手順:参考書学習⇒問題演習

学習の流れについては、まず参考書で内容の理解に努め、問題演習で記憶を定着させつつ、解答力をつけるのが良いでしょう。
最初から問題演習に入ると
・全く問題が解けずに挫折してしまう
・体系的な学習ができない
・理解が深まらず応用問題に対応できない
といった危険性が生じます。
これまで法律関係の勉強をしたことが無い人は特に陥りやすいので、参考書⇒問題演習の流れで学習を進めることをおすすめします。
参考書を使った具体的な学習方法、学習効率が爆増する問題集の使い方は
にまとめております。
実践練習:過去問演習、模試演習

問題演習で実力が付いたら、過去問演習、模試演習に入りましょう。
その際、制限時間を設け、水分補給や携帯電話を使用しない等、なるべく本試験に近い形で行うとより一層効果的です。
この模試演習で合格基準点(180点)以上を安定して取れるようになると、ほぼ行政書士試験に合格できると思います。
記述抜きで140点以下の場合は、模試の復習をしつつ、参考書学習や問題演習に戻って理解を深めましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここまでの内容を理解すれば、行政書士試験に独学で挑む際の具体的な始め方、その後の勉強法がイメージできたのではないかなと思います。
これから勉強を始める方も、既に学習を始めている方も当記事を参考いただき、合格の一助としていただければ幸いです。
尚、記載内容についてご不明な点等ございましたら、お気軽に掲示板もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。