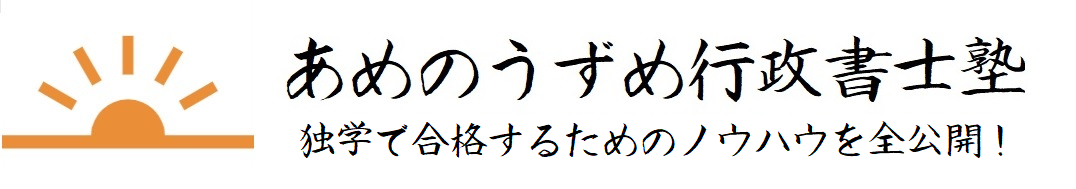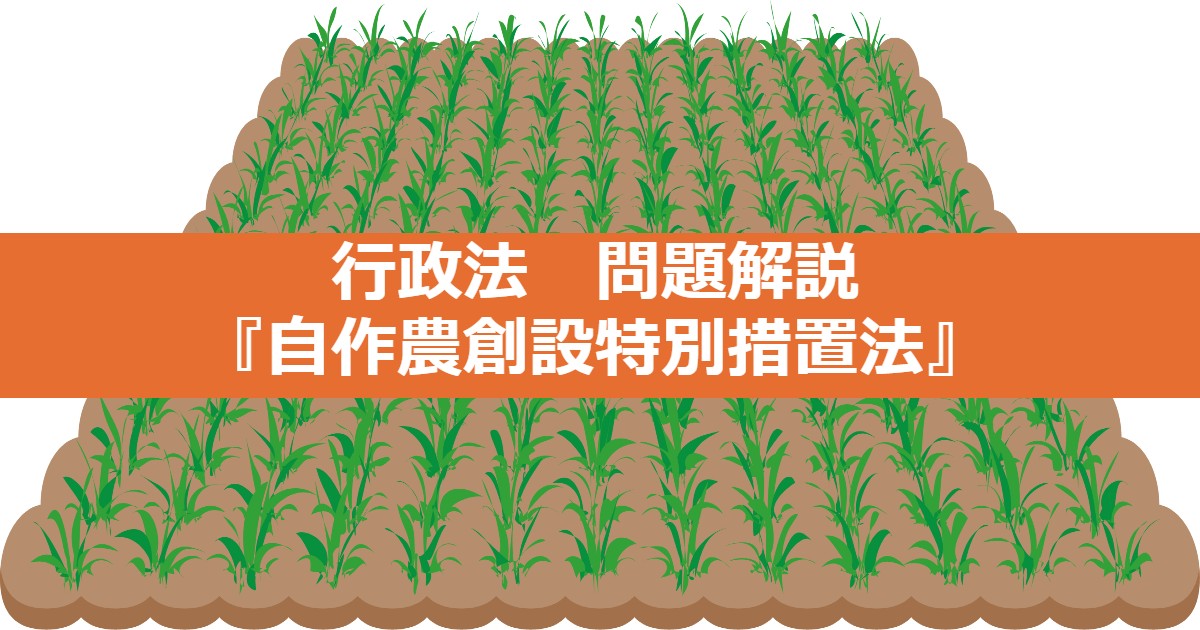行政書士試験の民法が難しい・・・
行政法がなかなか理解できない。
なんでこの答えになるのかわからない・・・。
そんな時は当サイトに質問いただければ わかりやすく解説いたします。
この記事では、当サイトご利用者様から実際にいただいた行政法の問題を回答&解説いたします。
記事を読み終えたころには、きっと理解が深まっていることでしょう!
※行政法を最速で得意にする裏技最近は、安価で高品質な通信講座も増えており、行政法の基礎を固めるなら東京法経学院の最短合格講座で学んだほうが早いかもです。 東京法経学院は7.5時間の無料体験も行っており、これを使って基礎をがっつり固めるのもありですね。
>>>東京法経学院
行政書士試験 行政法 『自作農創設特別措置法』
『自作農創設特別措置法』問題
Q:自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受任しなければならない。○か×か。
『自作農創設特別措置法』問題 解説
このままではわかりにくいので、理解しやすいように翻訳してみます。
Q: 国は『自作農創設特別措置法』という法律を使って、国民の農地を大量に買い上げたいと考えている。しかしながら、農地の数が多すぎて1件1件確認するのでは事務処理に時間がかかりすぎてしまう。
そこで『自作農創設特別措置法』では、登記簿に記載されている情報を使って買い上げる計画を立てることが認められており、この場合には、民法の対抗要件(登記を持っているものが勝つ)の規定が適用される。
そのため、登記簿上の持ち主が本当の持ち主と違っても、本当の持ち主は買い取りを受け入れなければならない。○か×か。
ということになります。この赤文字のところがポイントです。
『自作農創設特別措置法』問題 考え方
問題なのは、この場面で 民法の対抗要件(登記を持っているものが勝つ)規定が適用されれば本当の持ち主が悲しい事態に陥るということです。
どういうことか説明します。
恐らく本当の所有者はお金を払って農地を買ったはずです。
しかし、どういうワケか登記が売主の名義のままになっている。
その状態で『民法の対抗要件の規定(民法177条)』が適用されるなら、本当の持ち主は所有権を主張できないことになります。
そうなると、農地を手放さなければならない上に、その補償金は登記簿上の持ち主(=売主)に入るという阿鼻叫喚の事態になります。
農地だけ奪われて補償がない事態に見舞われる。これではあまりにひどすぎますね。
そこで判例はこう示しています。
『自作農創設特別措置法』 の 農地買収処分は、国が権力を使って農地を強制的に買い上げるものだから、民法上の売買(=私人間の売買)とは本質が違う。だから民法の対抗要件の規定は適用されない。
政府が『自作農創設特別措置法』を使って農地の買収を行う場合は、単に登記簿の記載だけで判断し、登記簿上の所有者を相手方として買収処分を行うべきものではなく、真実の農地の所有者からこれを買収すべきものであると解する。
ですから答えは『×』です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の問題もそうですが、法令科目の問題では内容自体は難しくないけれども、法律独自の表現でわかりにくくなっていることがよくあります。
日々の問題演習でいかに問題文をわかりやすくできるかを練習し、得点力アップにつなげていきましょう。
■こちらの記事では、わかりにくい問題を簡単に理解する方法を2つ紹介しています。
■地方自治法のわかりやすい解説はこちらの記事をご確認ください。

■聴聞のわかりやすい解説はこちらの記事をご確認ください。