そもそも農地法って何?何のためにあるの?
当記事ではそんな疑問にお答えすべく、農地法の目的と主な内容についてご紹介いたします。
この記事を読めば、農地法の全体像がざっくりと把握できます。
それでは見ていきましょう。
農地法の目的
農地法の目的は、農地法第一条に記載されています。
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229
これをざっくりと訳すと・・・
・食料生産に欠かせない農地を農地以外のものにできないように規制する。
・農地を効率よく利用できる耕作者に権利を取得しやすくする。
・農地が適切に利用できるように調整する。
これにより耕作者を守ると同時に食料生産量を増やし、国民が安定して食料を手に入れられるようにする。
つまり、食料が国民に安定的に行きわたるよう、農地の保護と耕作者を保護することが農地法の目的です。
農地法で保護される農地には2種類あります。「農地」と「採草放牧地」です。
どのような違いがあるか、見ていきましょう。
農地とは

農地とは、耕作の目的に使われる土地をいいます。農業を行うための土地ですね。
この農地には、現在使われていなくても耕作しようと思えばすぐに耕作できる土地
=休耕地や耕作放棄地も含まれます。
また、登記上の名目が「農地」であれば、現在の状況に関係なく「農地」として扱われます。
例えば、家が建っている土地は通常「宅地」として扱われますが、登記上の名目が「農地」の場合は「農地」として扱われることがあります。
採草放牧地とは

採草放牧地とは、農地以外の土地で、耕作又は養畜のための採草又は家畜の放牧の目的のために使われる土地の事です。
堆肥や飼料の材料となる草を採るための土地、家畜の放牧を行うための土地です。
牧草を育てるための土地は、採草放牧地ではなく農地の扱いになります。
「農地」と「採草放牧地」の違いが分かったところで、どういう場面で農地法が使われるのかを見ていきましょう。
農地法の適用場面
農地法が登場する場面は主に3つあります。
1:農地の売買・貸借等、権利移転をする場合(農地法3条)
2:農地所有者が、農地を農地以外のものにする場合(農地法4条)
3:農地の権利移転後、農地を農地以外のものにする場合(農地法5条)
自分の農地を自分で耕作する時以外はほぼ全て農地法が関係してきます。
仮に農地法の許可を受けずに売買契約がなされた場合、その契約は無効となります。
さらに、農地法違反で処罰される可能性もありますので十分注意しましょう。
農地法違反の罰則
農地法に違反した場合の罰則は非常に重いです。
農地法第六十四条を見てみましょう。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者
農地法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229
重大な罪を犯した時と同程度の罰を科されることになります。
農地に関する取引を行う場合は必ず農地法にも注意を払うようにしましょう。
まとめ
これまでの人生で農地になじみがなかった方にとっては驚きの内容だったかもしれません。
・新しく農業を始めたい方
・農地を相続した方
・農地に家を建てる計画がある方等
はこれから農地法が関係する場面が出てくると考えられます。
後々のトラブルを避けるためにも是非一度、農地転用に詳しい行政書士にご相談ください。
なお、農地法3条、4条、5条についてはこちらの記事に記載しておりますので、目を通してみてください。
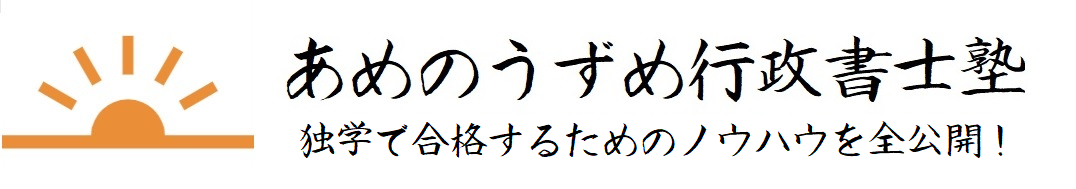



コメント