・行政法に苦手意識がある
・行政法の点が伸び悩んでいる
・行政法の勉強法がわからない
このようなことでお悩みではありませんか?
行政法が苦手だと途端に行政書士試験の合格が難しくなります。
そこで今回の記事では、行政法が苦手な方でも得点力をアップさせる方法をお伝えします。
まず行政法でつまづいてしまう理由を知ることから始め、それを解決するための方法をお伝えした後、おすすめの勉強法のご紹介といった流れでお話します。
私自身も行政法がなかなか得点できなかった経験がありましたが、なぜ得点できないかを考えたことによって克服し、高い時で9割、低くても8割程度は平均して得点できるようになりました。
同じような境遇の方にとっては、参考になる内容も多いと思います。
今回紹介する情報を役立てていただければ幸いです。
なお、行政法の配点等の試験情報や、攻略法等はこちらの記事で紹介していますので、
本記事と併せて目を通してくださいね。
行政法でつまづく理由
行政法で扱う内容自体は、民法や憲法等と同じく私たちの生活に近いものです。
例えば公務員は行政法の法律や規則を基に活動していますし、車の免許や営業許可、国家賠償法等も行政法の範囲内です。
数学と異なり、あまり馴染みが無くて理解できない類のものではありません。
ではなぜ苦手意識を抱いてしまうのか。一般的に考えられる理由は3つあります。
1つ目は、言葉の意味を正確に区別できていないこと
2つ目は、理解が曖昧
3つ目は、判例や条文の知識が曖昧
3つに共通するポイントは正確に理解できていない、ということです。
順番に見ていきましょう。
言葉の意味を正確に区別できていない
行政法では行政機関や行政庁、棄却と却下といった似たような用語が度々登場します。
詳しい説明は別記事で行っているためここでは割愛しますが、
これらの違いが正確にわかっていないと、文章の意味を読み違えたり、選択問題や記述問題で対象を間違えることに繋がり、失点してしまいます。
※行政機関についてはこちらの記事で解説していますのでご確認ください。
理解が曖昧である
行政法では内容にそこまで難しいものがない分、引っかけ問題が数多く出題されます。
例えば行政不服審査法の審理手続きと行政手続法の聴聞手続きの違いや行政事件訴訟法の抗告訴訟、当事者訴訟等の法定抗告訴訟の内容の違い、提起する場面の違い等、受験生を混乱させる論点が多いのです。
なんとなくの知識はあるが、正確な理解ができていない受験生はここでふるい落とされてしまいます。
概要や流れといった幹の部分はしっかりと把握した上で、そこに付随する知識の肉付けをきっちりと行う必要があります。
判例や条文の知識が曖昧である
行政書士試験の行政法では判例や条文を基にした問題がよく出題されます。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法といった重要法令は条文知識が5肢択一問題や多肢選択問題でそのまま問われることもあり、正確な条文理解が必要です。
判例もよく出題されます。特に重要な判例については、その内容はもちろん、論点や結果、裁判所の判決理由まで正確に学習することをおすすめします。
なお、重要な判例は繰り返し出題されていることが多いので過去問をみればわかりますし、必ずテキストや問題集で詳しく解説されています。
行政法の対策について
行政法の対策は心構えにあります。正確な理解を心掛けましょう。
曖昧な理解で終わらせることは避け、わからないところは理解できるまで調べ、復習する。
これを日々の学習で癖づけることが大事です。
予備校、通信講座を利用している人は、講義を受講時、あるいは、テキストで理解できない箇所があれば、どこが理解できないのかを明確にした上で、講師や担当者に逐一質問し、理解の徹底に努めましょう。
独学の人は、参考書で徹底的にインプットを行い、問題演習や後に紹介する方法を通して理解の精度向上に努めましょう。
ちなみに参考書に記載されている内容以外が出題されることはほぼありません。
出版社によって参考書に書かれている内容が全く違う、なんてこともほとんどありませんので、自分に合った教材を使ってインプット作業を行えば全く問題ありません。
行政法の勉強法
おすすめの勉強法は二つあります。
1つ目は過去問を使った勉強法
2つ目はあめのうずめ行政書士講座オリジナルの勉強法
です。
行政法には過去問を使った勉強が効果的
過去問中心の対策が非常に効果的です。
行政法はある程度出題範囲が決まっており、また、重要な論点や条文、判例については過去に何度も出題されている可能性が非常に高いです。
というのも、行政法では毎年5肢択一問題が19問出題されており、単純計算で19×5(肢)で95問の問題が出題されていることになります。数が多いことから、重要な論点はあらかた網羅されているというわけです。
今後も過去問と似た出題が予想されること、重要な論点は過去問でほぼすべて網羅できることから、過去に出された問題とその肢を一つ一つ理由を付けて正誤を判断できるようになれば、それだけで8割近く得点できる力が身につきます。
行政法に関しては主に過去問を活用しましょう。
あめのうずめ行政書士講座オリジナルの勉強法
あめのうずめ行政書士講座が考案した方法で、白紙に一連の流れや内容を書き出す勉強法がおすすめです。
この方法を使えば、自分の理解度を確認できると同時に、その分野の関連知識まで一気にまとめて復習でき、効率良く学習を進められます。
まっさらな状態から確認したい分野の流れや重要語句をひたすら書き出します。
フロー図にしても良いですし、箇条書きでも構いません。
そして書き出したものとテキストや本の内容を比較し、一致しているかどうか、重要な論点が抜けていないかを確認します。
抜けているところがあれば、なぜそれが抜けたのかその理由を考え、同じ間違いを犯さない注意しつつ、テキストを読んで抜けた箇所を覚え直す作業を行います。
これを繰り返すだけで行政法の基礎が固まり、安定して得点できるようになるでしょう。
効果爆増の最高の問題集
過去問と併用すれば行政法をほぼ完璧にできる最高の書籍が存在します。
それがこちら。

この問題集は頻出条文・判例の重要な語句の部分が穴埋め形式になっており、問題を解くことで条文・判例の大切な語句を丸々覚えることができるという優れものです。
同じように条文、判例から出題される民法、憲法にも対応している為、これ1冊で行政書士試験の法令科目の基礎をマスターできる効率のよい問題集です。
注意点として、この1冊を完璧にするには相当な時間が掛かります。
独学者で、かつ、試験まで時間がある方は是非使ってみてください。
解答の精度が格段に上がること間違いなしです。
行政法対策まとめ
行政書士試験の行政法は、ある程度出題傾向が固まっていますし、内容的には難易度はそこまで高くありません。対策についても比較的容易です。
しかし、似たような制度や語句、論点が多く、受験生を混乱させるような引っかけ問題が数多く出題されています。
とにもかくにも正確な理解が求められます。
司法書士試験や社会保険労務士試験等の他の資格試験では細かい部分まで正確な暗記を要求されますが、行政書士試験の行政法に限って言えば同じことが言えます。
語句の意味はもちろん、重要条文、重要判例に加え、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法といった重要な法律については細部まで理解することを心掛けてください。
これができれば行政法は攻略したも同然です。
行政法が得点できなくて困っている方や行政法が苦手な方は是非、当記事で紹介した方法を試してくださいね。
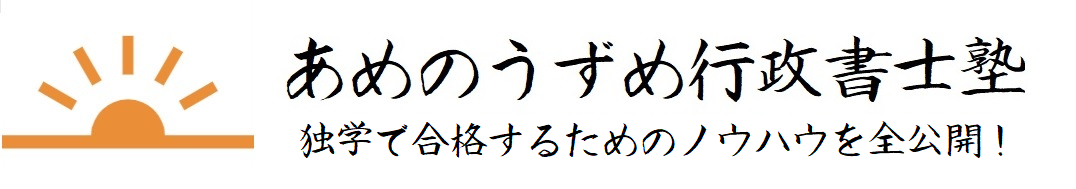





コメント