行政書士試験に合格するにはどうすればよいか。
この質問に答えるべく、今回の記事では合格するために大切なことについてお伝えいたします。
決められた期間で行政書士試験に合格するには効率良く勉強することが必要であり、自分に合った戦略を練る必要があります。
私が受験生の時に知りたかった内容、役に立った内容を中心にご紹介いたします。
この記事を読めば、行政書士試験に合格するためのがつかめます。
なお、行政書士試験に短期間で合格するための勉強法についてはこちらの記事で紹介しています。
行政書士試験の心構え
行政書士試験を攻略するには、まず心構えを知ることが大事です。
いくつかのポイントに分けて解説していきます。
早めに勉強を始める
可能であれば早めに勉強を始めましょう。
早めに始めた分だけ合格に近づきます。
自分の実力は 勉強効率×勉強量 で決まります。
自分に合った勉強法を確立している人でなければ、勉強法を見つけるまでにある程度時間がかかるはずです。
その意味でも勉強量は確保できた方が有利です。
行政書士試験を舐めない
大前提として、現在の行政書士試験は間違いなく難しい部類に入ります。
・行政書士試験の合格率は毎年10%前後であること
(この受験者の中には、司法試験、司法書士試験、公務員試験の受験者も含まれます。)
・一般的に合格に必要な勉強時間は500~800時間程度とされていること
これらの事実がそれを証明しています。
しかし、ネット上の行政書士試験の評価は、
「難しい」というものと、「簡単」というものの2つに分かれています。
矛盾するようですが、これらもまた正しい評価です。
行政書士試験は資格試験の中では難関資格ですが、これはあくまで他の一般的な資格と比較した場合です。
行政書士と同じく士業として分類される弁護士や司法書士、弁理士、税理士などの超難関資格と比較すると、行政書士は簡単な部類に入ります。
つまり、試験の難易度は比較対象によって変わるということです。
司法書士試験受験生から見ると行政書士試験は簡単ですし、宅建試験受験生からすれば行政書士試験は難しいとなります。
上位資格の受験者でもない限り、行政書士試験は相応の学習時間、学習量を確保しなければ合格できない試験である。という認識を持つことが大事です。
継続することを第一に
行政書士試験を途中で挫折される方の多くは、勉強が続かない事が理由です。
行政書士試験の受験を決意したら、試験勉強を始める前に、毎日勉強を継続する方法について考えてみてください。
これができれば行政書士試験合格に大きく近づきます。
行政書士試験の攻略にはある程度の学習時間、学習量が求められます。
あくまで目安ですが、合格に必要な勉強時間は500~800時間程度と言われています。
この目安を基準とした場合、毎日10時間勉強すれば2カ月弱という短期間で合格できる計算です。
しかしながら、時間を自由に使えて、かつ、勉強の習慣がある人でもない限りこれは現実的ではありません。
日々お仕事をされている方や主婦業をされている方が確保できる平均的な勉強時間は1日2~3時間程度ではないでしょうか。
このたった2~3時間の勉強時間でも、毎日継続するのはとても難しいです。
少し油断すると、
勉強する気が起きない⇒サボり癖が付く⇒勉強時間が不足する⇒成績が伸びない⇒楽しくない⇒勉強する気が起きない・・・
という悪循環に陥り、結果挫折してしまいます。
それを避ける為にも勉強する気が起きない時の対策を早い段階で考えておく必要があります。
身近な人の意見や合格者の体験記等、いろんな意見を参考にして自分に合った対処法を見つけてください。
当サイトでも勉強を続ける秘訣についてこちらの記事で紹介していますので、併せて読んでみてください。
模試で一喜一憂しない
一般的に、模試は実力を測る重要なものですが、行政書士試験においては少し意味合いが異なると考えます。
大学入試や他の資格試験のように相対評価型の試験であれば、他の受験生との実力差を知ることは非常に大事ですが、行政書士試験は絶対評価型の試験であり、他者と比較することにあまり意味はないというのが理由です。
行政書士試験の模試は、本試験の雰囲気を味わうもの、時間配分を知るもの、新しい問題に触れるものといった意味合いが強いと私は考えています。
※相対評価・・・個人の学力を、ある一定の集団内の相対的位置によって評価する方法
※絶対評価・・・設定された教育目標に対し、個人がどれだけ達成したかを評価する方法。到達度評価。
引用: デジタル大辞泉
特に市販の模試は、予想問題集とあるように「本試験で出題されそうな問題」を収録したものであり、「受験生の実力を測る」ことに重きをおいていません。
当てにいく問題集ですから、今までに出題されたことのない論点を問うものや重箱の隅をつつく問題が数多く収録されています。
過去問中心の問題集で学習を進めた方が思うように得点できないのはある意味当然であり、合格基準点に届かなくてもなんら問題はありません。
行政書士試験においては、模試の結果で一喜一憂する必要はまったくないのです。
それよりも、間違えた問題の復習はもちろん、時間の使い方や会場の雰囲気に慣れる練習として活用することをおすすめします。
裏技、語呂合わせに頼りすぎない
行政書士試験は、特に行政法や民法、憲法といった法律系の科目においては法的思考力が求められます。
多肢選択式や記述式等、一つの論点でも問い方は様々であり、暗記で乗り切るのは労力、効率双方の観点からおすすめできません。
法令科目、例えば民法では、その導き出される結果に合理的な理由が存在します。

- 作者:中澤 功史/コンデックス情報研究所
- 出版社:成美堂出版
- 発売日: 2020年01月28日頃
こちらの本のような肢の正誤を判断するテクニックや、語呂合わせといったものは最終手段として活用するに留め、日々の学習の中では、その合理的な理由を理解する練習をしましょう。
それだけで法令科目の成績は格段に向上します。
※合理的というのは筋が通っていること、誰もが納得できることをいいます。
法的思考力を習得する方法についてはこちらの記事で紹介しています。
100点を目指さない
行政書士試験は300点満点中、180点以上の得点で合格です。
6割でいいのです。何も8割、9割を取る必要はありません。
100点を目指すのはメリットよりもデメリットの方が大きいです。
行政法の得点を9割から満点にするには、5割から6割にあげるのとは比べ物にならないくらい大変です。時間もかかるため、他の科目がおろそかになってしまう危険性があります。
苦手な科目をカバーするために得意科目で満点を目指すよりも、得意な分野は安定して8割から9割の得点率となる程度に留め、苦手な分野を6割程度まで得点できるように対策する方が合格に近づきます。
行政書士試験の学習技術
テキスト選びや問題集、過去問の使い方は、勉強効率を大きく左右します。
そこで、特に重要な参考書・問題集・過去問について、その選び方や使い方を紹介します。
テキスト選びは大切
テキストの質という意味ではどの出版社のものも変わりはありませんが、勉強の効率という点で大きく差が生まれます。
人にとって分かりやすい参考書でも自分にとってはイマイチだった、ということはあり得ます。
ネット上の評判だけで決めるのではなく、本屋に足を運び、自分の目で、自分にとってわかりやすいテキスト、参考書を選ぶようにしましょう。
ただし、教材によっては誤りの内容が記載されているものもありますので、購入前にAmazonや楽天のレビューを確認することをおすすめします。
問題集の使い方が合否を分ける
何度も同じ問題を間違えてしまう経験はございませんか。
この経験が頻繁にある方は、もしかするともったいない問題集の使い方をしている可能性があります。
問題集の使い方は超重要です。使い方次第で、行政書士試験の合否を分けるといっても過言ではありません。
その一例として、ただ単に問題集の回数をこなす、といった使い方があります。
周回すればするほど正答率は上がります。が、これは答えを覚えてしまったことによる可能性が高いです。
問題集を使う際には、何故間違えたのか。何故この選択肢が正解なのか、その理由を考え、理解することが大切です。
繰り返した数は少なくても、一つ一つの問題の肢が正解、不正解である理由を説明できるようになるまで丁寧に活用した方が確実に実力が付きます。
問題集を1周するには大きな労力と時間を費やします。
時間と労力という大切な資源を極力無駄にしないためにも、二度と同じ問題を間違えないようにするにはどうすればよいか、を考えながら学習を進めるようにしましょう。
学習効率を最大にする問題集の使い方についてはこちらの記事で紹介しています。
過去問の使い方
行政書士試験においても過去問を使った学習は非常に有効です。
特に基礎法学や行政法、民法、憲法、商法・会社法といった法令科目、個人情報保護分野は、過去に出題された内容がそのまま出題されることもあります。
反対に、政治・経済・社会分野、情報通信分野、文章理解分野等一般知識科目については過去問中心の学習はおすすめできません。
というのも2度同じ問題、近い内容の問題が出題される可能性はほぼゼロに等しいためです。
これらの分野は、出題形式や傾向を知るという使い方に留め、別の問題集や予想問題集等で学習されることをおすすめします。
行政法の対策についてはこちらの記事で紹介しています。
行政書士試験 合格するには まとめ
いかがでしたでしょうか。
行政書士試験に合格するには効率良く勉強することが必要であり、自分に合った戦略を練る必要があります。
予備校や通信講座を利用されている方であれば、その教育機関ごとのカリキュラムが存在し、講師等から効率の良い勉強法についても指導を受ける機会もあるかもしれませんが、独学の方はどちらも自分でみつけなければなりません。
そこで、この記事で紹介した内容が、効率の良い勉強法、自分に合った戦略を練る為のヒントになれば幸いです。
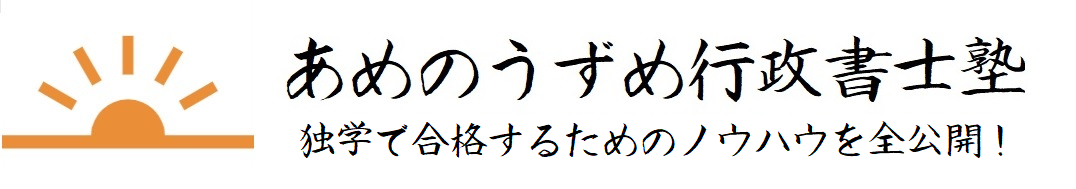



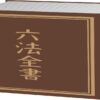




コメント